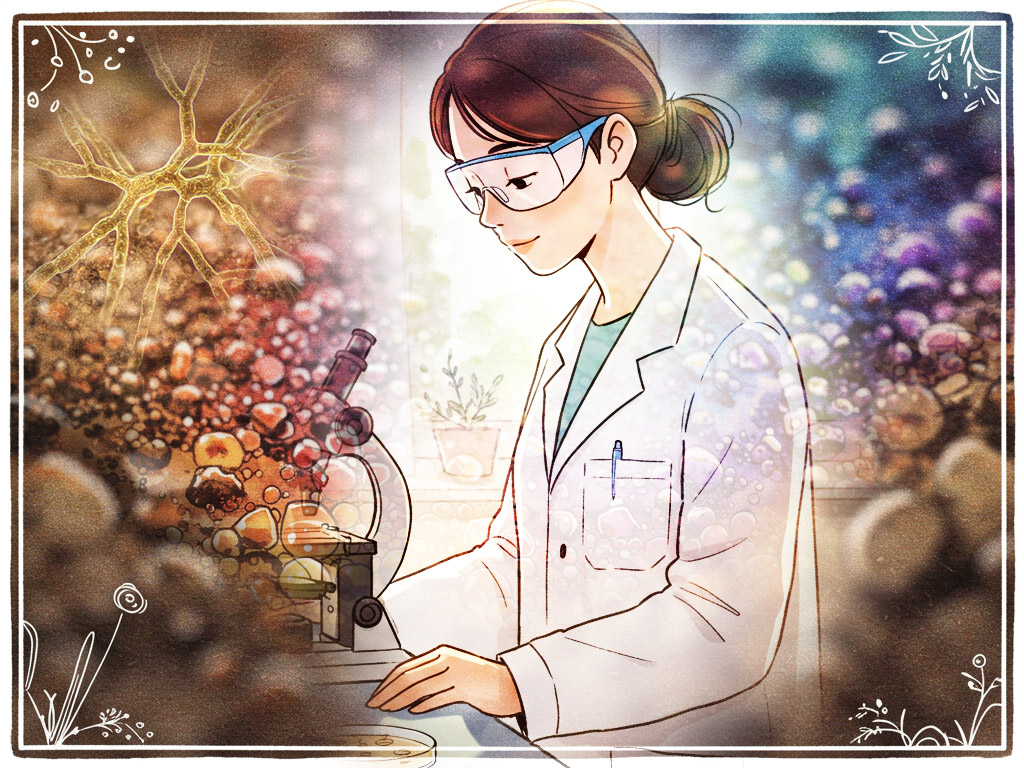
土壌化学性と土壌病害のフシギな関係 ~知っておきたい対策のヒント~
みなさんこんにちは!株式会社ホーネンアグリの坂野秀人です。本格的な農繁期に向けて、弊社でも生産のピークを迎えようとしています。この春の育苗、そしてその後の生育から収穫まで、農家の皆様をしっかりとサポートしていきたいと考えております。
さて、今回のブログでは、「土壌の化学性」と「土壌病害」の関係について解説いたします。一口に土壌病害といっても、カビや細菌、ウィルス、センチュウなど、その原因は様々です。連作障害や土壌病害に悩まされている方も多いのではないでしょうか?土壌消毒を繰り返しても、なかなか解決しない…そんな経験はありませんか?
実は、土壌病害は、病原菌(病原体)だけが原因ではありません。私たち人間が風邪をひくときに、日ごろの疲労や不摂生、栄養不足などが背景にあるように、土壌病害のあるところ、他の要素が密接にかかわっていることが多いようです。今回は、土壌の化学性に注目し、土壌病害との関係を紐解いていきたいと思います。

土壌pHと微生物の活動
土壌pH(酸度)が作物の生育にとって重要で、作物ごとに最適なpHの範囲があることはよく知られているかと思います。これは主に、pHの変化に伴って様々な成分が溶解、あるいは不溶化することで、植物にとって都合が良い環境かどうかが変わることに由来しています。
ところで、土壌微生物にとっても好みのpH領域があるのをご存じでしょうか。やや一般論になってしまいますが、基本的には中性域近くで土壌微生物は活発に活動し、特に細菌類は中性を好むものが多いようです。土壌病原菌の好むpHといえば・・・
● 糸状菌類:
中性域~弱酸性で最も活発に活動します。土壌病害の大多数は糸状菌由来です。アブラナ科のネコブ病菌はpHが7.2以上(の弱アルカリ性)になると急激に発病頻度が低下すると言われています。
● ジャガイモそうか病:
原因はいわゆる放線菌の仲間ですが、中性からアルカリ性で多発するため、おおむねpH5.0以下の酸性にするのが良いとされています。
このように、作物に被害を与える病原体は、それぞれ活動しやすいpHがあるため、土壌酸度をその作物に応じた適正値に矯正することが大切だと言えます。
リン酸とアルミニウムの関係
リン酸は必須かつ大量に要求される肥料です。特にリン酸吸収係数が高い、黒ボク土や火山灰土壌では土壌にリン酸が固定されがちなので、多めに施用することも多いかと思います。ただ、窒素やカリ、カルシウムなどが何らかの経路で土壌の下層に溶脱(水に乗って移動)していく一方で、リン酸は土壌中のアルミニウムなどと結合して土壌中に固体で残留・蓄積しやすいことに注意が必要です。
なぜなら、リン酸過剰は土壌病害を助長、あるいは悪化させる場合があるからです。過剰なリン酸は土壌中の活性アルミナ(可溶性アルミニウム)と結合し、アルミニウムがもつ病害抑止力を低下させるそうです。(※)例えば・・・
●根こぶ病:
根こぶ病が発病しにくい黒ボク土には多量のアロフェン(アルミニウムを含む粘土の一種)を含まれており、根こぶ病の休眠胞子を捕まえて離さない性質があります。ところが、リン酸が過剰だとこの性質が低下し、病原体が自由に動き回れるようになります。結果として根こぶ病が激発する場合があります。
●ウリ科のホモプシス根腐病やジャガイモそうか病など:
リン酸過剰で発病しやすくなるという報告があります。
アルミニウムは植物にとってたいへんなストレス、毒性があるものですが、土壌病害を引き起こす微生物にとっても抑止力として作用しているとは・・・一筋縄でいかないというか、なんとも不思議な存在ですね。
肥料成分の過不足・・・バランスが重要
このブログをご覧の皆様はよくご存じかと思いますが、肥料成分の過不足が土壌病害を助長する要因となる場合があります。
●カルシウム、ケイ酸、マンガン、ホウ素不足:
植物の細胞壁(まさに防壁)を形成する要素が不足すると土壌病害に対する耐性が低下してしまいます。
●窒素過剰:
植物は軟弱に育つ傾向があり、結果として土壌病害の影響を受けやすくなってしまいます。窒素が過剰な場合は、上記の植物体内の「防壁」の量が相対的に小さくなるため、更に土壌病害虫耐性の低下に拍車がかかります。
●微量要素の銅不足:
細胞壁の硬い部分(リグニン)の形成に関わっているうえに、直接的な殺菌効果もある銅が欠乏すると土壌病害につながる要因となります。
土壌分析で土壌の健康状態をチェック!
いかがでしょうか。土壌化学性の乱れが土壌にとって危険であることが改めて確認できたかと思います。土壌病害対策には農薬や対抗作物、物理性の改善など様々なアプローチがありますが、複数の手法を組み合わせた総合的防除が重要だと言われています。
土壌化学性を適正にする第一歩は土壌分析を行ってその圃場の「現在地」を知ることです。土壌分析をされていない方は、ぜひ一度分析することをお勧めいたします。その際、生育の良い個所と悪い個所を分析して比較することが有効です。どのような成分バランスにするのが最適なのか知る道標になることでしょう。皆様の圃場で病気に負けない強い植物が育つことを願っております!
株式会社ホーネンアグリ 坂野(土壌医)
※参考:
『土づくりと土壌微生物 過度な土づくりが土壌病害を助長する-園芸土壌のリン酸過剰に対する警鐘-』 土づくりとエコ農業 2011年 後藤逸男
『ホモプシス根腐病の発病に及ぼす土壌の種類,施肥リン酸,土壌pHの影響』 日本土壌肥料学雑誌 2015年 大島宏行,前田良之,後藤逸男
『園芸土壌のリン酸過剰がもたらす弊害とその対策』 2016年 後藤逸男


